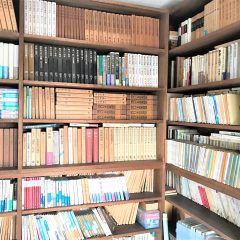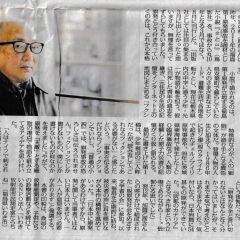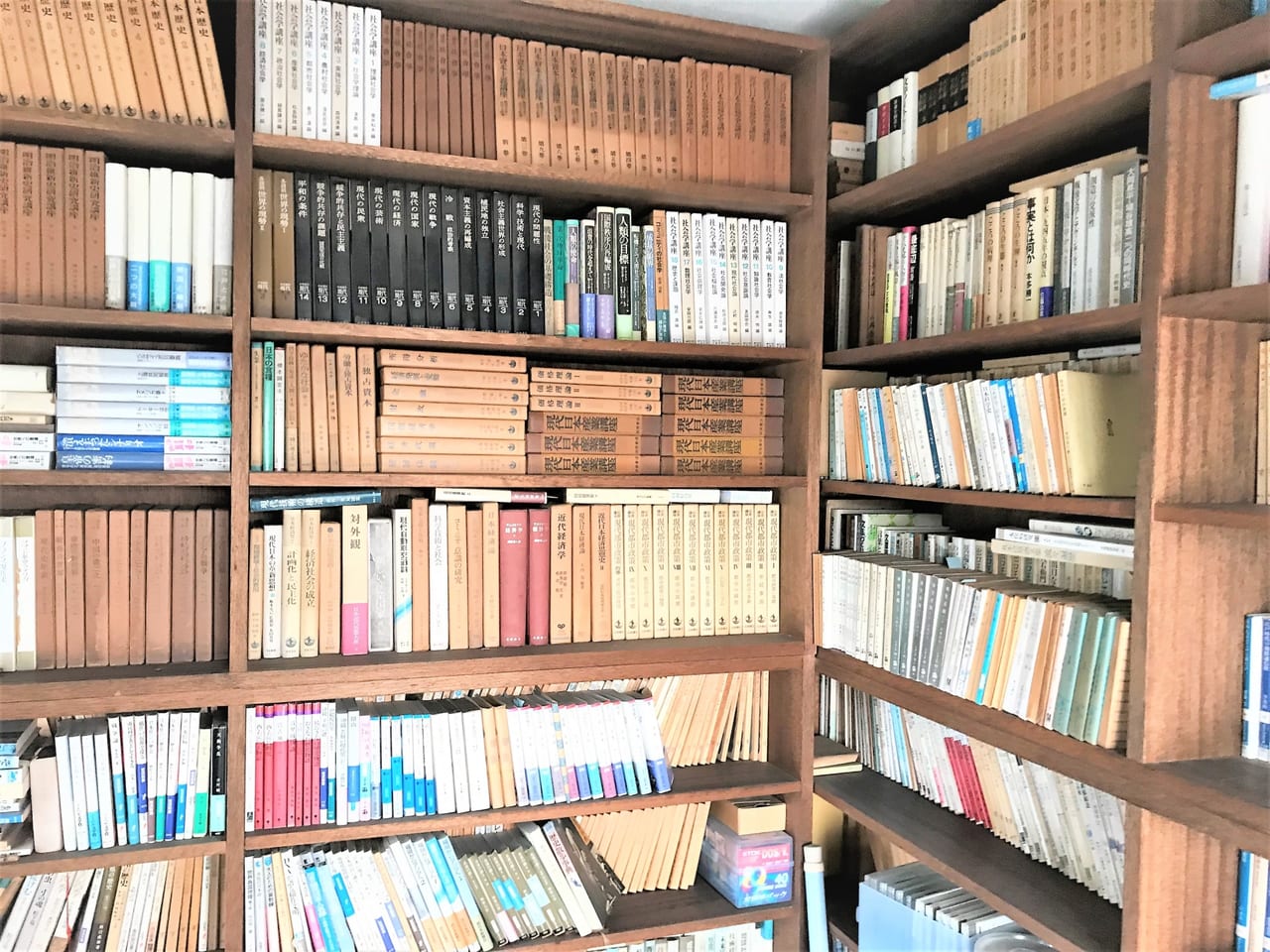
ムラマサ小説道場開講10周年所感
小説に救われた――僕の率直な実感だ。昭和の高度経済成長期の恩恵が、いまだ及ばない地方の小さな町で生まれ、近くの本屋で漫画本や文学書を手にするようになった。実家は貧しかったけれど、なぜか、僕は本だけは買うことができた。
母子家庭に育ったので、家計を支えたのは母だったが、この人には、「漫画ばっかり読んで」、「小説ばっかり読んで」と、いつも叱られていた。働きに出ている母に代わって、僕を育ててくれたのは祖母だった。この人は、近くの紡績工場でパートをしていて、僕に小遣いをくれた。それが本を買う原資になった。
祖母は、ほぼ読み書きのできない無筆の人で、そのせいか僕が本屋に通うことはうれしかったようだ。小説家になりたいと言い出して、母が大反対するなか、賛成してくれたのも祖母だった。
といっても、小説家がどのような仕事で、デビューするのがどれだけ難しいかなど知らず、かわいい孫の僕が小説家になりたいというのだから、わけも分からずに賛成したらしい、とあとで知った。
僕は小学校のころから学校が嫌いで、中学に入ると、年間で150日ぐらい休んだ。週休二日制、とうそぶいていた。けれど、本だけは読んだ。ある友達は、村上の本棚は新刊書の本屋の棚と、古本屋の棚とがつながっていて、ループ運動をしているといった。
それは正しかった。僕は新刊書を読み終えると、古本屋へ持っていて買い入れてもらい、そこで得たお金で新刊書を買った。ときには、古本屋で欲しい本を見つけて買うこともあった。
だから、新刊書の本屋の棚にあった本が、僕の本棚に並び、それがいつの間にか古本屋の棚に並ぶ。そして、古本屋の棚に並んでいた本が、僕の本棚にさされる。自分の本棚が好きな本で埋まってゆくのは楽しかった。
取り柄は読書から、いつか文章を書くほうへ変わっていった。高校生のころには、友達の読書感想文を代筆して原稿料をもらった(これが、僕が初めて文章をお金に変えた体験になる)。
高校は中退した。そのときには小説家になると決めていた。
父は酒乱で、酒で内臓がめちゃめちゃになって死んだ。30歳だった。母は、ママさんと呼ばれる仕事をしていた。店の客らしき男たちが、たまに僕の家に泊まった。祖母は気丈な人で、私生児の父を独りで育てた。
母と祖母はしょっちゅう諍いをして、僕を苦しませた。生きているのが嫌になって、20歳のときに、徹夜で遺書を書いた。けれど、朝になってそれを読み返し、死ぬのが馬鹿馬鹿しくなった。
僕がやるのは自分を殺すことではない。小説家になることだ。そう思った。それから紆余曲折を経て大学へ進学し、子供たちに勉強を教える塾を開いた。夕刻から働いて、家に帰って朝まで小説を書いて、午後まで眠る。やがて僕はある大手文芸誌の新人賞をもらって、作家デビューを果たした。続けて5回、芥川賞の候補になって、文壇に認知された。
もし、小説がなければ、僕は、とうにこの世にいない。デビューする前もそうだったが、デビュー後もずっと、生きるために小説を書いてきた。この、生きる、というのは、生活費を稼ぐことも含まれているけれど、人間として存在するため、という意味のほうが大きい。
生きるために小説を書く人たちの導き手になりたいと思ったのは、10年前のことだ。それで「ムラマサ小説道場」を開講した。この間、受講生の2人が大手出版社の新人賞を受けてデビューした。
もちろん、まだデビューしていない人も多い。しかし大手出版社から商業デビューすることだけが、「ムラマサ小説道場」のめざすものではない。他人からは趣味の領域とみなされても、小説を書くことが生きることとつながっている人は、ほんとうの小説家だ。
生きるために小説を書く――自分がそうだったように、小説に救われる人たちを、これからも支えてゆきたい。
ムラマサ小説道場主宰・村上政彦